(2)当時最大のメディアだった塩化ビニール製アナログ・レコードは、マスタリングの際に位相に注意を払わないと針飛びを起こす代物だった。
(3)メジャー・レーベル(含むCBS・ソニー)の場合、演歌もポップスも邦楽/洋楽もすべて同じエンジニアが担当していた。つまりエンジニアにとって録音機材の管理、メンテナンスは非常に重要だった。それに加え、塩ビ盤へのマスタリングでイコライジングを施す際に重要となる「RIAA曲線」についてミュージシャンは理解していない、ということ(=まともなマスタリングの仕方を知らないだろうという見方)。この2点から当時のエンジニアはミュージシャンがミキサー卓に触るのを極力嫌った。
(4)以上のような録音技術のノウハウを、ミュージシャン自身が熟知していなかった。
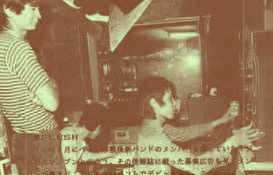
1979年6月 S-KENスタジオにて
