 |
| リザード年代記『彼岸の王国』 (テレグラフ TG-022/1985.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
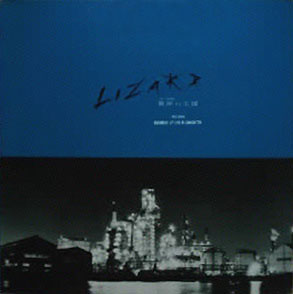
|
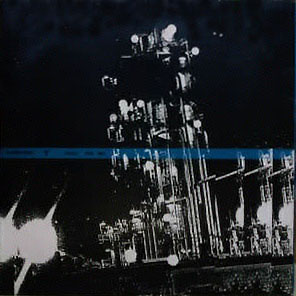
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| front | back
| [A] LONDON SIDE | Live at THE NASHVILLE ROOM [B] TOKYO SIDE | チキンシャックII/ローディ・プラザ 1. ROBOT LOVE
| 1. デストロイヤー
| 2. DON'T TOUCH THE SWITCHBOARD
| 2. 甘い誘惑
| 3. PLASTIC DREAMS
| 3. キツネつき
| 4. REAL GOOD TIME ※
| 4. チャンス
| 5. GUYANA
| 5. 王国
| 6. LOVE SONG
| (6. 月光価千金)・・・not credited
| 7. ROCK CRITICS
| 1.〜4. 福生チキンシャックII | 1978.3.25(カセット録音) 8. MACHINE-GUN KID
| 5. 有楽町日立ローディ・プラザ 1979.6
| Recorded live at THE NASHVILLE ROOM, | LONDON 1979.8.3(Fri.) カセット録音 6. スタジオ・デモ 1980
| LIZARD
| 菅原庸介(モモヨ)
| Vox/Guitar<TOKYO SIDE>
| 塚本勝己(カツ)
| Guitar
| 若林一彦(ワカ)
| Bass
| 中島幸一郎(コウ)
| Keyboard, Synthesizer
| 若林恒夫(ツネ)
| Drums<TOKYO SIDE>
| 吉本孝(ベル)
| Drums<LONDON SIDE>
| | |
|
 
|
蜥蜴の雨やどり(HOME)
|
モモヨ作品集INDEX
|
web master:space_ape | |
|---|
